(民俗2の12)
『書紀』天孫降下の条に先駆者還りて曰く、〈一の神有りて、天八達之衢に居り、その鼻長さ七咫脊の長さ七尺云々、また口尻明り耀れり、眼は八咫鏡の如くして、※然[#「赤+色」、124-3]赤酸醤に似れり、すなわち従の神を遣して往きて問わしむ、時に八十万の神あり、皆目勝ちて相問うことを得ず、天鈿女すなわちその胸乳を露にかきいでて、裳帯を臍の下に抑れて、咲 いて向きて立つ〉、その名を問うて猿田彦大神なるを知り、〈鈿女復問いて曰く、汝や将我に先だちて行かむ、将我や汝に先だちて行かむ、対えて曰く吾先だちて啓き行かむ云々、因りて曰く我を発顕しつるは汝なり、故汝我を送りて到りませ、と〉とて、伊勢の狭長田五十鈴川上に送られ行くとあるは、猿田彦の邪視八十万神の眼の堪え能わざるところなりしを、天鈿女醜を露したので猿田彦そこを見詰めて、眼毒が弱り和らぎ、鈿女打ち勝ちて彼をして皇孫の一行を避けて遠地に自竄せしめたのだ。
いて向きて立つ〉、その名を問うて猿田彦大神なるを知り、〈鈿女復問いて曰く、汝や将我に先だちて行かむ、将我や汝に先だちて行かむ、対えて曰く吾先だちて啓き行かむ云々、因りて曰く我を発顕しつるは汝なり、故汝我を送りて到りませ、と〉とて、伊勢の狭長田五十鈴川上に送られ行くとあるは、猿田彦の邪視八十万神の眼の堪え能わざるところなりしを、天鈿女醜を露したので猿田彦そこを見詰めて、眼毒が弱り和らぎ、鈿女打ち勝ちて彼をして皇孫の一行を避けて遠地に自竄せしめたのだ。
インドでハヌマン猴神よく邪視を防ぐとて祭る事も、青面金剛崇拝は幾分ハヌマン崇拝より出た事も既に述べた。それが本邦に渡来してあたかも邪視もっとも強力なりし猿田彦崇拝と合して昨今の庚申崇拝が出来たので、毒よく毒を制する理窟から、以前より道祖神と祀られて邪視防禦に効あった猿田彦が、庚申と完成された上は一層強力の眼毒もて悪人凶魅どもの眼毒を打ち破るのだ。庚申堂に捧ぐる三角の袋括り猿など、パンジャブ辺でも邪視を防ぐの具で、一つは庚申の避邪力を増さんため、一つは参詣者へ庚申の眼毒が強く中らぬべき備えと知らる。またインドや欧州その他に人畜が陰陽の相を露せる像を立て、邪鬼凶人の邪視を防ぐ例すこぶる多く、本邦にも少なからず、就中猴が根を露せるもの多し。
その諸例は今年九月印刷出口君の『日本生殖器崇拝略説』に詳載さる。予出口君の許しを得て珍しき猴の石像の写真をここに掲げんとせしも再考の末見合せ、代りに掲ぐる第十一図は余が南ケンシントン博物館で写真を模したもので、多くのインド人に尋ねしも訳分らず、しかし道祖神の一態たる和合神(『天野政徳随筆』一に図あり)のインド製に相違なかろう。
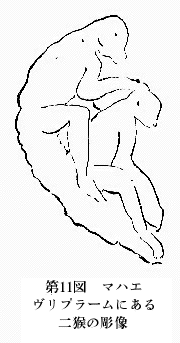
猴を馬厩に維ぐ事については柳田君の『山島民譚集』に詳説あり、重複を厭いここにはかの書に見えぬ事のみなるべく出そう。『広益俗説弁』その他に、この事、『稗海』に、晋の趙固の馬、病みしを郭璞の勧めにより猴と馴れしめて癒えたとあるに基づくといえど、『梅村載筆』には猿を厩に維ぐは馬によしという事、『周礼註疏』にありと記す。現に座右にあれどちょっと多冊でその文を見出さず。註にあらば晋より前、後漢の時既にこの説あったはずだが、疏にあらば晋より後のはずでいずれとも今分らぬ。
しかし『淵鑑類函』四三二、後漢王延寿王孫賦、既に酔い眠った猴を縛り帰って庭厩に繋ぐとあれば、郭璞に始まったとは大啌だ。それから、伊勢貞丈、武士、厩の神を知りたる人少なしとて、『諸社根元記』と『扶桑略記』より延喜天徳頃左右馬寮に坐せし、生馬の神、保馬の神を挙げ、『書紀』の保食神牛馬を生じたるよりこの二神号を帯びたのだろといった(『あふひづくり』上)、この二神は猴でなかろう。
『塵添 嚢抄』四、猿を馬の守りとて馬屋に掛くるは如何、猿を山父、馬を山子といえば、父子の義を以て守りとするか、ただし馬櫪神とて厩神在す、両足下に猿と鶺鴒とを蹈ませて二手に剣を持たしめたり、宋朝にはこれを馬の守りとす、この神の踏ませるものなれば猿ばかりをも用ゆるにや。橘守国の『写宝袋』にその像を出せるが『
嚢抄』四、猿を馬の守りとて馬屋に掛くるは如何、猿を山父、馬を山子といえば、父子の義を以て守りとするか、ただし馬櫪神とて厩神在す、両足下に猿と鶺鴒とを蹈ませて二手に剣を持たしめたり、宋朝にはこれを馬の守りとす、この神の踏ませるものなれば猿ばかりをも用ゆるにや。橘守国の『写宝袋』にその像を出せるが『 嚢抄』の所記と違う。柳田氏は猿を添うるは判っているが、鶺鴒の意味分らず、あるいは馬神と水神との相互関係を推測せしむる料にあらずやといわれたが、川柳に「鶺鴒も一度教へて呆れ果て」、どど一にも「神に教えた鶺鴒よりもおしの番いが羨まし」ナント詠んだごとく、この鳥特異の動作を示して二尊に高尚なる学課を授け参らせたに因って、「逢ふ事を、稲負せ鳥の教へずば、人を恋に惑はましやは」それを聞き伝えたものか、嬌女神ヴィナスの異態てふアマトンテの半男女神はこの鳥を使者とし、その信徒に媚薬として珍重された。
嚢抄』の所記と違う。柳田氏は猿を添うるは判っているが、鶺鴒の意味分らず、あるいは馬神と水神との相互関係を推測せしむる料にあらずやといわれたが、川柳に「鶺鴒も一度教へて呆れ果て」、どど一にも「神に教えた鶺鴒よりもおしの番いが羨まし」ナント詠んだごとく、この鳥特異の動作を示して二尊に高尚なる学課を授け参らせたに因って、「逢ふ事を、稲負せ鳥の教へずば、人を恋に惑はましやは」それを聞き伝えたものか、嬌女神ヴィナスの異態てふアマトンテの半男女神はこの鳥を使者とし、その信徒に媚薬として珍重された。
今村鞆君元山府尹たり、近く『増補朝鮮風俗集』を恵贈さる。内に言えるは鮮人の思想貧弱にして恋愛文学なく、その男女の事を叙するや「これと通ず」「これを御す」と卑野露骨にして憚らずと。それについての鄙見は他日に譲り差し当り述ぶるは、『淮南子』に〈景陽酒に淫し、髪を被りて婦人を御し、諸侯を威服す〉。その他古文に〈婦女を御す〉というが多い。これは鹿爪らしい六芸の礼楽射御の御とは別にしてしかも同源の語で、腰を動かすてふ本義だ。所詮鶺鴒の絶えず尾を振るごとくせば、御馬の術も上達すてふ徴象で、さてこそ馬の災を除く猴とこの鳥を踏んで、馬櫪神よく馬を養いよく馬を御すと示したのだ。何と畏れ入ったろう。
back next
![]()
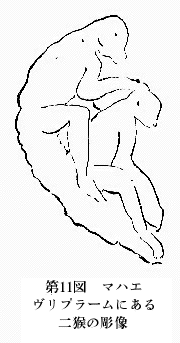
![]() 嚢抄
嚢抄![]() 嚢抄』の所記と違う。柳田氏は猿を添うるは判っているが、鶺鴒の意味分らず、あるいは馬神と水神との相互関係を推測せしむる料にあらずやといわれたが、川柳に「鶺鴒も一度教へて呆れ果て」、どど
嚢抄』の所記と違う。柳田氏は猿を添うるは判っているが、鶺鴒の意味分らず、あるいは馬神と水神との相互関係を推測せしむる料にあらずやといわれたが、川柳に「鶺鴒も一度教へて呆れ果て」、どど